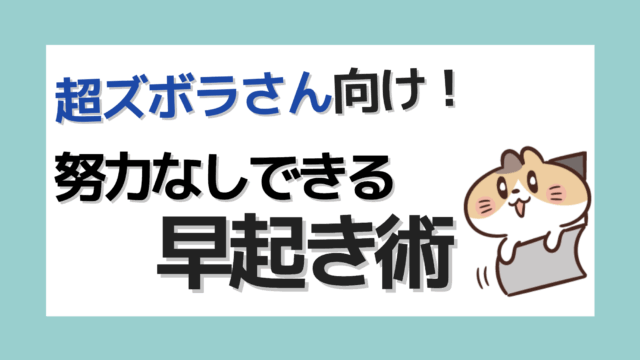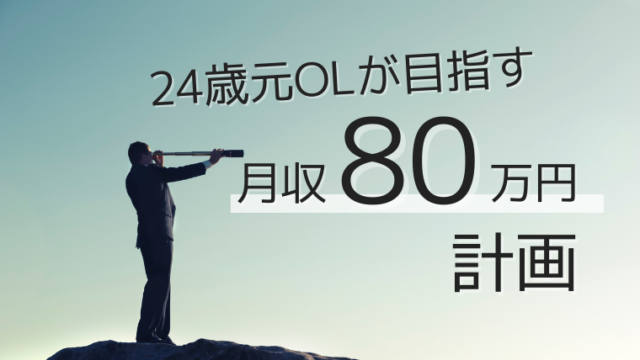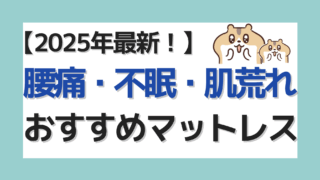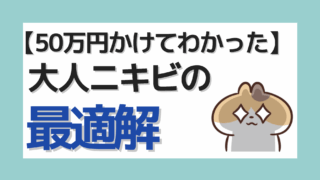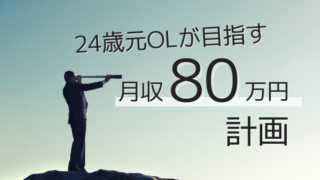「なんだか最近ずっとだるい…」「朝起きるのがつらい」「仕事に行くのが憂うつ」。
それ、もしかすると五月病かもしれません。
特に新しい環境に飛び込んだばかりの人にとって、五月病の抜け出し方がわからず、ひとりで抱え込んでしまうケースは少なくありません。
実は私も以前、毎日がつらくて、「怠けてるのかな…?」と自分を責めていた時期がありました。
でも、五月病の意外な事実と抜け出し方を知ったら無理なく頑張ることができるようになったんです!
この記事では、五月病の抜け出し方に悩んでいる方に向けて、よくある誤解や見落としがちな原因、五月病の抜け出し方としてすぐに試せる「ある習慣の見直し」まで、わかりやすく解説します。
読み終えたとき、少しでも心が軽くなるような内容をお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
「五月病の抜け出し方を知りたいけど、何から始めればいいかわからない…」
そんなあなたにこそ、この記事を読んでいただきたいです!
五月病の意外な事実
1. 「五月病」は病名じゃないって知ってた?
「五月病」は、医学的に正式な病名ではありません。
実は5月に環境の変化やストレス、疲れが原因で心身の不調をきたす人が多く総称したものが五月病と呼ばれるようになりました。
病院で診断されるとしたら「適応障害」や「うつ状態」となるケースもあります。
つまり、軽い気持ちでスルーしてしまうのは危険ということ。
「なんとなく不調」「気分が上がらない」そのサインは、脳や心が出している“休ませて”というサインかもしれません。
2. 頑張った人ほど5月に不調が出やすい理由
「五月病なんて、私怠けてるのかな…」そんな風に自分を責めていませんか?
実は逆で、4月に人一倍頑張った人ほど五月病になりやすいんです。
新しい職場、新しい人間関係、新しい仕事──慣れないことを1ヶ月間、無理して頑張ってきたあなた。
その疲れが、ちょうど5月になってどっと押し寄せているのです。
まずは自分を責める前に、ここまで頑張ってきた自分をちゃんと労わってあげてください。
3. 真面目で気配り上手な人ほど陥りやすい
五月病になりやすい人の特徴、それは「真面目」な人。
「もっと頑張らなきゃ」
「早く仕事を覚えなきゃ」
「周りに迷惑かけないようにしなきゃ」
こんな風に、常に周囲を気にして気を張り詰めている人ほど、知らず知らずのうちに限界を迎えてしまいます。
特に女性は“空気を読む力”に長けているからこそ、心の疲れを抱え込みやすい傾向が。
「頑張りすぎてないかな?」と、今一度自分に問いかけてみてください。
4. 不調の原因は“気持ち”ではなく“脳の疲れ”
「何もしたくない」「職場に行きたくない」──
そんな状態になったとき、よく「気の持ちよう」や「根性論」で片づけられがちですよね。
でも、それはあなたのせいではありません。
これは「脳の疲労」によるもの。
脳が過度なストレスを感じて、あなたに「休んで!」という指令を出している状態です。
つまり、「やる気が出ない」「だるい」と感じるのは、あなたが弱いからではなく、ちゃんと働いた証拠。
まずはそのサインに気づき、自分を責めるのをやめましょう。
今日からできる!五月病の対策法5選
1. 朝日を浴びる
朝日を浴びることから、1日を始めましょう。
「えっ、それだけ?」と思うかもしれませんが、実は朝日には脳と心に大きな影響を与える力があります。
それは「セロトニン」という幸せホルモン。
朝日を浴びるとセロトニンの分泌が活性化し、気持ちが前向きになったり、脳のスイッチが自然と入ったりします。
さらに、朝に余裕があると
-
少し贅沢な朝ごはんを食べられたり
-
散歩に出かけたり
-
カフェに行けたり
と、リフレッシュできる時間を作ることもできます。
「朝起きるのがつらい…」という人は、自動でカーテンを開けてくれるアイテムを取り入れてみるのも一つの手です。設定した時間に合わせてカーテンが自動で開き、朝日を自然に取り入れることで、無理なく目覚めやすくなります。
外の光とともに目を覚ます感覚は、アラーム音よりもストレスが少なく、1日を気持ちよくスタートできるきっかけになります👇
2. SNSを見すぎない
休日くらいは、InstagramやXなどのSNSから少し距離を置いてみましょう。
SNSはどうしても「他人のキラキラした部分」ばかりが目に入ります。
「みんなは頑張ってるのに、なんで私は…」と、自分を責めるきっかけになってしまうことも。
比較して落ち込むくらいなら、見ないほうがずっと心にやさしいです。
SNSを断つことで、思った以上に心が軽くなることもありますよ。
もし「スマホを触らずに過ごす時間」を作りたいなら、読書の時間を設けるのもおすすめです。
心が落ち着くエッセイや、考えすぎる自分にやさしくなれる本など、自分に合った1冊を選ぶだけで、気分転換になります👇
3. 軽く体を動かす
体を動かすことで、脳内に「エンドルフィン」や「ドーパミン」といった快楽物質が分泌され、自然と気分が上向きになります。
といっても、激しい運動をする必要はありません。
-
10分だけストレッチする
-
軽く散歩に出る
-
ヨガやラジオ体操をしてみる
といった「心地よい」と思えるレベルでOKです。
体を動かすことで血流も良くなり、思考もスッキリ。
気分の切り替えにも効果的なので、ぜひ日常に取り入れてみてください。
ヨガやストレッチが初めての人には、ヨガグッズやDVD付きのヨガ本など、自宅で始められるツールもあります👇
4. 睡眠リズムを整える
睡眠不足や生活リズムの乱れは、脳にとって大きなストレスになります。
夜ふかしをして起床時間がズレると、体内時計が狂い、セロトニンの分泌も不安定になってしまいます。
まずは以下を意識してみましょう:
-
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
-
寝る前にスマホやPCの光を浴びすぎない
-
寝る直前はリラックスできる音楽やアロマを取り入れる
「朝起きて、夜眠る」当たり前のことが、心と脳の健康にとって一番の土台なんです。
そんなときは、眠りに入りやすい環境づくりがカギです。部屋の照明を落として、アロマやお香でリラックスできる空間にすると、自然と眠りにつきやすくなります。
寝る前の10分。心を落ち着ける香りで、睡眠の質を上げてみませんか?おすすめのお香はこちら👇
5. 自分を責めず「疲れて当然」と声をかける
不調を感じたとき、
「私ってダメだな…」「サボってるのかな…」と、自分を責めていませんか?
でも、それは間違い。
あなたが感じているその不調は、ちゃんと頑張った証拠です。
4月の1ヶ月間、環境の変化に適応しようと必死に踏ん張ってきた脳と心が、少し休みを求めているだけ。
「疲れて当然だよ」「よくここまで頑張ったね」と、
親友にかけるような言葉を、自分自身にもかけてあげてください。
それだけでも、不思議と心がゆるんでいきます。
心を落ち着ける時間には、ジャーナリング(書く瞑想)もおすすめです。専用のノートに、その日の気持ちをただ書き出すだけで、思考の整理になります。
気持ちを吐き出せるジャーナリングノートはこちら👇
まとめ|“不調の理由”がわかれば、それだけで少し楽になる
五月病は、心の弱さではなく、「頑張ってきた脳と心の疲労」からくる自然な反応です。
-
朝日を浴びる
-
SNSから少し離れる
-
軽く体を動かす
-
睡眠のリズムを整える
-
自分にやさしい言葉をかける
どれもシンプルなことですが、積み重ねれば確実に心が軽くなっていきます。
「自分はダメなんだ」と責めるのではなく、
「疲れてるだけなんだ」と受け入れることから、回復は始まります。
あなたの不調に“名前”がついたことで、少しでも心がラクになりますように。
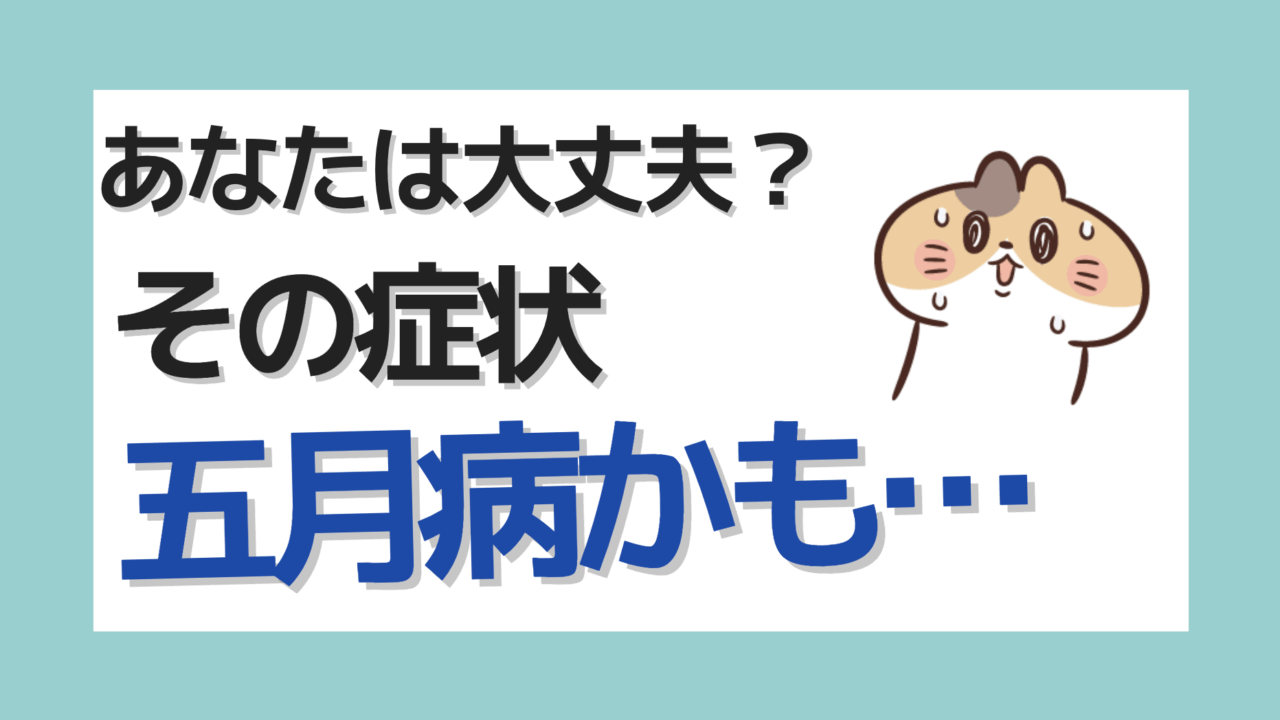
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806ac1b.f7ea600b.4806ac1c.91924812/?me_id=1415408&item_id=10000115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fswitchbot%2Fcabinet%2F10069132%2Fimgrc0078272289.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806b388.a800ad39.4806b389.993fa4a7/?me_id=1285657&item_id=11072949&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00483%2Fbk4478025819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806e6ab.7cf00d7e.4806e6ac.740a6544/?me_id=1411864&item_id=10636820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooks-ogaki%2Fcabinet%2Ftanpin41%2F9784801400535.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806ecb2.8be7bd16.4806ecb3.64121dd8/?me_id=1314546&item_id=10000806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fibiki-kenkyujyo%2Fcabinet%2F10613866%2F0984_240501_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806f031.4284e538.4806f032.1e9dadb7/?me_id=1212316&item_id=10007120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnoellamp%2Fcabinet%2Fnipponkodo%2Fs-kayuragi600-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4806f3f2.03edb376.4806f3f3.3dcb2a70/?me_id=1429302&item_id=10000128&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasahiruyoru%2Fcabinet%2F11371679%2F11777940_1000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)